「環境と福祉の基盤となる『コミュニティ』の効用」を公開しました。- 白井信雄教授の連載「環境と福祉 問題解決のための「統合」とは」
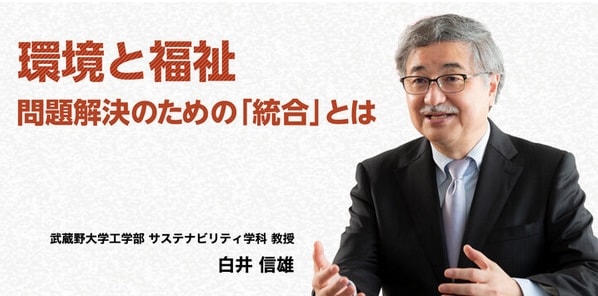
武蔵野大学工学部サステナビリティ学科白井信雄教授が講談社が運営するウェブサイト 講談社SDGs by C-stationでの連載「環境と福祉 問題解決のための「統合」とは」にて、「環境と福祉の基盤となる『コミュニティ』の効用」と題した最新記事を公開しました。
記事の内容は下記になります。
コミュニティとは「人と人のつながり」のこと。コミュニティには多様な側面があります。マッキーヴァーは、コミュニティの定義を「場所や空間を共有する結合の形式で、地縁による自生的な共同生活」としましたが、今日では、この定義は地域コミュニティという1つのタイプを指すものとなりました。
産業化により職場コミュニティが中心となった時代もありましたが、都市化の進行やライフスタイルの多様化によって地域コミュニティとともに希薄化し、特定の目的や趣味等のテーマを共有する市民コミュニティの活動が活発になってきました。
さらに、インターネットの普及、通信容量の拡大、メタバースの普及により、インターネット・コミュニティ、サイバースペース上のバーチャル・コミュニティも形成されてきました。メタバース上のコミュニティでは、現実世界とは違うキャラクターを持ったアバターとしてふるまうことができ、現実世界とは異なる新たなつながりの場となっています。
これらの多様なコミュニティは、それぞれに環境問題・環境対策と相互作用の関係にあります。具体的な事例を示していきましょう。
この記事の内容
- 公害による地域コミュニティの分断と再生
- 「地元学」を通じた人と自然、人と人のつながりの再生
- 環境をテーマにした市民コミュニティ~市民共同発電の例
- 気候市民会議ならぬ「気候コミュニティ会議」への注目
- デジタルプラットフォームを活用した環境コミュティの可能性
- コミュニティ主導の壁を超えるために
環境と福祉の基盤となる「コミュニティ」の効用|環境と福祉 問題解決のための「統合」とは【第17回】|講談社SDGs by C-stationより
ぜひ、読んでみてください。詳しくはこちら
環境と福祉の基盤となる「コミュニティ」の効用|環境と福祉 問題解決のための「統合」とは【第17回】|講談社SDGs by C-station







