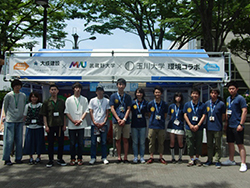環境と経済の統合で遅れをとった日本
日本は雑巾を絞り切っている?
日本と欧州連合(EU)・ドイツを比較してよくいわれることの一つが、「日本はすでに世界一の省エネ国であり、エネルギー効率の高い国である。 EU やドイツはまだ日本よりも効率を上げる余地があるが、 日本はすでに雑巾を絞り切っており、 これ以上のエネルギー効率の改善や温室効果ガスの削減は費用が大変高くつく。安易に EU やドイツに追随することは経済的に引き合わず現実的ではない」 というものです。
実は、10 年前、私が行政の世界を離れ、京都大学の経済研究所に移った頃は、私も「もしかしたら、そうかも」と漠然と思っていました。 しかしながら、経済研究所で研究を始めるにあたり、 日本企業の実態を知らないことには新たな政策提言もできないということで、二人の若く優秀なポスドク研究員とともに、 まずは、企業の実態調査から研究をスタートしました。
以降、3 年にわたり、東証、大証上場の全企業へのアンケート調査の実施と、環境会計ガイドラインに基づき温室効果ガスの削減量とその費用を公開している環境報告書の分析を行いました。 その結果は、私が当初思っていたものとはかなり異なるものでした。
紙数の関係で、詳しくは拙著『低炭素化時代の日本の選択』 (岩波書店、2008 年) をお読みいただきたいのですが、主な結論は以下のとおりです。
① 日本企業は、平均的には、いまだ費用をかけないでも温室効果ガスを減らせる余地があること
② 産業界の自主的な削減行動では、今後温室効果ガスの大幅な削減は期待できないこと
③ 政府の将来的な削減政策は、 企業の削減行動に大きな影響を与えること
具体的な例を挙げると、 日本企業の多くは、明らかに初期投資が回収できるような省エネ投資ですら、必ずしも行っていないという実態がわかってきました。
日本の先進企業と ドイツの共通点
それでは、なぜ、 日本の多くの企業はそのような省エネ投資などを行わないのでしょうか。私は、そのヒントはリコーの環境経営やドイツのエネルギー改革にあるのではないかと思っています。
ご承知のように、 リコーは、複写機のメーカーですが、ここには環境保全を企業の社会的・経済的な存続条件と考える、信念とリーダーシップを持ったトップがおられました。すなわち、社員に対して、「リコーグループの温室効果ガスは絶対値で削減しろ、同時に、売上げを伸ばし、利益も確保しろ」 というものです。日本ではまだ、国の基本的な削減方針すら確立していなかった1990 年代の半ば頃のことです。
社員はトップの無茶苦茶な要求に頭を抱えたといいます。 これらの要求に対しては、小手先の改善努力では到底クリアできません。そのため、苦心の末、全社のあらゆる部門をあげて、 リコーがつくる複写機のすべての部品をリユースすることをベースとした、設計段階からの生産構造の徹底的な大改革を行いました。
その改革には費用と10 年余の時間がかかりました。 しかしながら、それが全面的に機能し、回収された機材のリサイクルが軌道に乗るに従い、かつて必要だった廃棄や新規部品のコストが劇的に下がり、極めて生産性の高い競争力のある企業体質が実現するとともに、 温室効果ガスの排出量も削減されたのです。
ドイツの考え方も、基本はリコーの環境経営の考え方と変わりません。すなわち、 ドイツの経済体質を変え、温室効果ガスを削減するための投資が必要なことを認め、それに要する時間をきちんと見込んだ上で、計画的にその大プロジェクトを進めているのです。
冒頭に述べた、「日本はすでに雑巾を絞り切っている。これ以上やることは、経済的に引き合わない」 という考え方と一つ決定的に違うのは、経済というものに対する根本的な見方だと私は思います。 すなわち、経済における技術やコストは決して固定的なものではなく、状況に応じてダイナミックに変化するという側面があります。前述したリコーのトップは、「現状に安住し挑戦をしなくなったらその企業は衰退する」 という考えを持たれていたと聞きますし、 ドイツのエネルギー・コンセプトで書かれているのも、「我々は、技術革新、成長、雇用の膨大なポテンシャルが引き出されるよう、このような道を定める」 という前向きな姿勢です。そして、このような政策が機能している背景には、私の研究の結論の一つでもある、「日本ですら雑巾は絞り切ってはいない」 という事実があると考えています。言葉を換えると、経済という雑巾からは永遠に水が絞れるのであり、絞り切ったと考えたとき、その国や企業の進歩が止まるということです。 また、リコーにしてもドイツにしても、このような大胆な改革が行われるその出発点が、 トップリーダーによる野心的で長期的な目標の設定です。国であれ企業であれ、それがきちんと設定され、国民や社員に支持されるかどうかが、その後の成果を規定するのです。
ところが、第二の点に関連しますが、 日本ではエネルギー政策と気候変動政策はきちんと調整・統合されていません。その象徴が、 これまでも、そして現在も進められている石炭火力です。 これは、世界のエネルギー事情の中で、石炭火力が短期的には比較的安いコストであったことと関係しています。 しかしながら、石炭や石油の価格とて長期には大きく変動します。 また、 電源構成の中で、最も温室効果ガスの排出量が多い石炭火力をこれから数十年社会に固定化することの是非が十分検討されているとはいえません。
原子力発電も同様です。そもそも、チェルノブイリや福島のような事故の可能性のある社会インフラを持つことの是非はもとより、安全性や放射性廃棄物にかかる長期的保管のコストと、現在急速にコストが下がりつつある再生可能エネルギーとの、中長期的なコストの比較の検討が日本では不足していると思います。
気候変動政策と原子力発電、 石炭火力発電
さて、以上のような観点から日本の気候変動政策を見ると、いくつかの問題点が見えてきます。第一は、日本の気候変動政策には長期的な視点が欠けていることです。第二は、経済政策、なかんずくエネルギー政策との統合の視点が欠けていることです。 第三は、民間の資金を含め、社会を変えていくための投資の流れを変えていくという視点が弱いことです。
温室効果ガスの削減を考えるとき、エネルギーの生産や消費のシステムとの関係は決定的に重要です。 とくに、大規模な発電所などは、原子力にしても火力にしても、 いったん作られると、それは数十年にわたって社会に組み込まれ、すぐに変更することは難しくなります。気候変動の安定化のように、2050年、2100 年といった長期の対策を考える上で、長期の電源構成をどうするかは大きな課題です。
社会を変えていくための投資とそのルール作り
現在の日本のような持続可能ではない社会を持続可能な社会に変えていくには、政府や民間を問わず、そのための費用、すなわち投資が必要です。 そのためには、政府による、方向性を持った意図的な市場への介入が必要です。 すなわち、持続可能な社会へ向かうための投資をより有利に、持続可能性を損なうような投資をより不利にする仕組みが必要です。 それが、経済的措置といわれている、環境税や炭素税、キャップ付き排出量取引制度などにほかなりません。
日本では、水俣病などの公害対策から環境政策がスタートしたため、 どうしても排出規制などの技術をベースとした規制的措置が環境政策の主流となってきました。そして、直接の利害が絡み、市場のルールを変える経済的措置には、経済界から反対の声が上げられてきました。 しかしながら、気候変動問題やさらには持続可能な発展というような根源的な問題に対しては、技術的な対応にとどまらず、お金の流れの変更を通じて、経済構造そのものを改革しなければ問題が解決しない時代になってきています。 日本でも、改めて国レベルでの持続可能性戦略を確立し直し、本格的な環境経済政策を進めていく必要があります。
※地球・人間環境フォーラム発行「グローバルネット2015年11月号」掲載、連載「21世紀の新環境政策論~人間と地球のための持続可能な経済とは」の記事を転載
一方井誠治(いっかたい せいじ)教授のプロフィール
1974年東京大学経済学部卒、75年環境庁(現環境省)入庁、 外務省在米大使館などを経て、2001年環境省政策評価広報課長、03年財務省神戸税関長、05年京都大学経済研究所教授、12年武蔵野大学環境学部教授、15年より武蔵野大学工学部環境システム学科教授 兼 武蔵野大学大学院環境学研究科長。京都大学博士(経済学)。環境庁計画調査室長として、94年版と95年版の環境白書を作成。専門分野は地球温暖化対策の経済的側面に関する調査研究、環境と経済の統合。著書に「低炭素化時代の日本の選択-環境経済政策と企業経営」など。